はじめに

高齢化が進む日本では、介護施設への入居希望者が年々増加しています。しかし、希望している施設への入居が叶わないケースも少なくありません。実際に申し込みをしても「入居をお断りします」と言われることがあり、家族としては大きなショックを受けることも。
老人ホームの入居拒否には、明確な理由と背景があります。本記事では、なぜ入居拒否が起こるのか、どのように対処すればいいのかを詳しく解説していきます。トラブルを未然に防ぎ、スムーズな入居を実現するためにも、知っておきたい知識を整理しておきましょう。
老人ホームの種類と入居基準

主な施設タイプと概要
老人ホームには複数のタイプがあり、それぞれで入居基準やサービス内容が異なります。
・特別養護老人ホーム(特養)
:要介護3以上の高齢者が対象。公的施設で比較的安価だが、入居待機者が多い。
・介護付き有料老人ホーム
:24時間介護体制が整った施設。要介護度に応じた手厚いケアが可能。
・住宅型有料老人ホーム
:生活支援が中心で、介護は外部サービスを利用。
・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
:バリアフリー設計で、見守り・安否確認サービスあり。
・グループホーム:認知症の方が対象。少人数で家庭的な環境の中で生活。
各施設の入居要件と優先順位
・要介護度:特養は要介護3以上が基本。要支援者は原則対象外。
・認知症の有無:グループホームは認知症診断が必要。一方で、認知症による問題行動で入居拒否されるケースも。
・医療的対応:胃ろう、インスリン、痰吸引などが必要な場合、対応できる施設は限られる。
老人ホームに入居を拒否される主な理由

医療的ケアの負担が大きい
入居希望者の健康状態が重篤で、施設側の看護・医療体制では対応しきれない場合、入居を断られることがあります。たとえば、以下のようなケースです。
こうした場合、医療対応可能な施設(ホスピス併設型や医療法人運営の老人ホームなど)を探す必要があります。
認知症や精神疾患による問題行動
こうした行動がある場合、「施設全体の安全と安定運営」の観点から入居が断られることがあります。
家族や本人の態度・対応が悪い
・面談時の対応が横柄で、施設スタッフと信頼関係が築けない
・家族が過干渉で、施設に過度な要求を繰り返す
老人ホームは「集団生活」です。協力的な姿勢がない場合、受け入れに慎重になる施設もあります。
支払い能力に不安がある
・月額費用の支払いが滞る可能性がある
・連帯保証人・身元引受人がいない
施設側も長期運営のため、経済的な信用がない場合はリスクとみなします。
空室状況と優先順位の問題
特養では要介護度や緊急性(自宅での介護が困難など)によって、待機者の中で入居順位が決まります。条件に合っていても、「優先度が低い」と判断されると後回しになる場合があります。
入居拒否は違法?法律的な位置づけ
入居契約は私的契約であり、施設に選定権がある
老人ホームの入居は「私的な契約」に該当します。施設側は契約自由の原則のもと、契約相手(入居者)を選ぶ権利があります。そのため、一定の合理的な理由があれば、入居を拒否することは合法とされています。
ただし、あくまで「合理的な理由」がある場合に限ります。
不当な差別的入居拒否は違法となる可能性も
施設側の入居拒否が次のような場合、問題となる可能性があります
このような場合は、憲法14条や障害者差別解消法、老人福祉法に抵触する可能性があります。
また、特別養護老人ホームなどの公的施設において不当な拒否があった場合、行政への相談が可能です。
入居拒否をされた場合の対処法

拒否理由を正確に確認する
まず、入居を断られた際には、その理由を明確に確認することが重要です。曖昧な説明しかない場合は、納得がいくまで質問し、文書で記録しておくと後の対応がしやすくなります。
医療対応可能な施設を探す
医療ニーズが理由で断られた場合は、以下のような施設を検討します
・看護師が24時間常駐している施設
・医療法人が運営している介護施設
・ホスピスや療養型医療施設
行動・症状を改善するケアを行う
認知症の症状が強い場合は、医師の診断を受けた上で、投薬治療や専門デイサービスの利用で改善を試みる方法もあります。
・デイケア(医療型の通所リハビリ)
・精神科・認知症外来の受診
支払い能力や保証体制の強化
・家族や親族による保証体制の提示
・成年後見人の選任
・財産・年金収入などの資産証明を明示する
専門家や支援機関への相談
入居拒否を避けるためにできる準備

入居拒否を未然に防ぐには、施設選びや入居時の対応において意識すべきポイントがあります。
複数の施設に事前申し込みをしておく
1つの施設に絞るのではなく、条件が合いそうな施設を複数候補として持ち、同時並行で申し込みを進めましょう。
・各施設の対応状況や入居条件を比較することで、より入居の可能性が高い選択肢を見つけやすくなります。
・「優先順位制度」がある施設では、今後の入居を見越して早めに申し込みを出しておくのも有効です。
病状や介護状況を正確に伝える
申込書や面談の場では、本人の状態を正確に、かつ前向きに伝えることが大切です。
・「介護が必要な理由」「現在の生活状況」「通院歴」「症状の変化」などを整理しておく
・認知症や精神疾患などがある場合は、主治医の診断書やケアマネージャーの意見書が役立ちます
面談・見学時の印象を良くする・家族の協力体制をアピールする
施設側は、入居者本人だけでなく、家族の対応も見ています。
といった協力体制を示すことで、信頼度が上がります。
まとめ
老人ホームの入居拒否は、「本人の状態」や「施設側の受け入れ体制」によって起こるものであり、誰にでも起こり得ることです。しかし、その多くは、事前の情報収集・準備・対応次第で回避できる可能性があります。
・医療ニーズ、認知症、家族対応などが入居拒否の原因となる
・施設側には契約自由の原則があり、入居の判断権がある
・拒否された場合は、理由を確認し、改善策や代替施設を探す
・家族の協力や正確な情報提供が、信頼と入居可能性を高める
入居を希望するすべての方が、安心して適切な施設にたどり着けるように、準備と柔軟な対応がなにより大切です。困ったときは、地域包括支援センターや専門家の力を借りることも検討しましょう。
公式LINEでの無料相談サービスの案内
ハートでは老人ホーム紹介会社として高齢者住まいアドバイザー、ファイナンシャルプランナー、不動産終活士が在籍しており完全無料で適切な介護施設をお探ししご提案しております。詳しく知りたい方、どの施設が最適かわからない方、自分に合ったサービスを探している方は、ハートの公式LINEからご相談ください。資格を持つ専門のスタッフが、あなたのニーズに合った情報を提供します。
✨こちらから公式LINEに登録して、ご相談ください!よくある質問(Q&A)
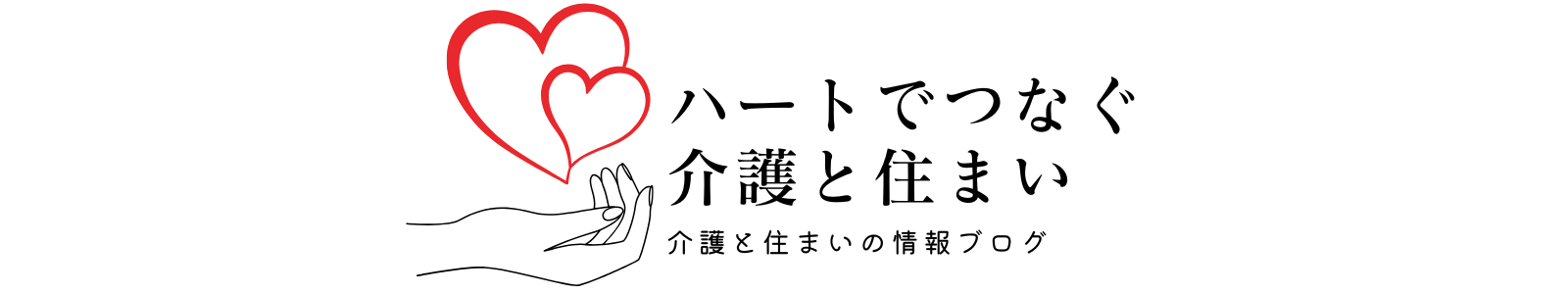




コメント