はじめに

介護施設にはさまざまな職種の職員が働いており、それぞれが専門的な役割を担っています。施設に入居する家族にとって、どの職員がどのような仕事をしているのかを知ることは、安心して施設を選び、適切なケアを受けるために重要です。
本記事では、介護士・看護師・相談員などの仕事内容、家族との関わり方、施設ごとの職員配置基準について詳しく解説します。
介護施設の主な職種と役割
介護士(介護職員)
介護士は、利用者の日常生活をサポートする役割を担います。主な業務内容は以下の通りです。
介護士は利用者と接する時間が最も長く、日々の変化に気づく重要な役割を果たします。
看護師(准看護師を含む)
看護師は、利用者の健康管理や医療行為を担当します。
施設によっては24時間体制で看護師が配置されていない場合もあり、その際は医療機関との連携が必要になります。
生活相談員(ソーシャルワーカー)
生活相談員は、利用者と家族の相談窓口として機能します。
相談員との関係をしっかり築くことで、家族が安心して施設と連携を取ることができます。
機能訓練指導員(リハビリ担当)
機能訓練指導員は、利用者の身体機能維持や回復を支援します。
施設によっては、理学療法士や作業療法士が常駐している場合もあります。
管理栄養士・調理員
管理栄養士は、利用者の健康状態に応じた食事を提供するための計画を立てます。
調理員は、実際に食事を作り提供する役割を担います。
施設長(管理者)
施設長は、施設全体の運営・管理を行います。
施設長は直接介護に関わることは少ないですが、全体の方針を決定する重要な役割を担っています
家族が知っておくべき職員との関わり方

介護士とのコミュニケーション
介護士は利用者と最も多く接する職員であり、家族との情報共有が重要です。
・日常生活の変化を定期的に確認する
・食事や睡眠の状況、体調の変化などを把握する。
・施設の連絡ノートを活用し、定期的にやりとりをする。
・介護方針について要望を伝える
・食事の好みやアレルギー、特定の介助方法の希望などを伝える。
・利用者の性格や好みを伝えることで、より良いケアが受けられる。
・施設でのケア内容について質問する
・介護士の業務範囲を理解し、適切な依頼をする。
・施設内での生活スケジュールを確認し、本人の希望に沿った対応が可能か相談する。看護師との関わり方
看護師との関わり方
看護師は利用者の健康管理を担当しており、病気や薬に関する情報を共有することが大切です。
・定期的に健康状態を確認する
・バイタルサイン(血圧・体温など)の変化を把握する。
・体調の変化があった場合、家族にすぐに連絡をもらえるよう依頼する。
・服薬管理や医療処置について相談する
・持病の管理方法について共有し、適切な対応を依頼する。
・施設内で対応できる医療処置と外部医療機関との連携方法を確認する。
・病院受診時の付き添いについて確認する
・施設の看護師が付き添う場合と家族が対応する場合のルールを把握する。
生活相談員との関係構築
生活相談員は施設と家族をつなぐ役割を持ち、入居後の手続きやトラブル対応を担当します。
・入居時の契約内容や施設のルールを理解する
・面会ルール、緊急時の対応、契約更新時の条件などを確認する。
・定期的に面談を行い、施設での生活状況を確認する
・相談員との定期的な面談を設定し、利用者の様子を詳しく聞く。
・介護サービスや手続きのサポートを受ける
・介護保険の更新手続きや、介護サービスの変更について相談する。
リハビリ職員(機能訓練指導員)との関わり方
機能訓練指導員と協力することで、利用者の身体機能をできるだけ維持し、生活の質を向上させることができます。
・リハビリの目標や進捗を確認する
・施設で提供されるリハビリ内容を把握し、家族として協力できることを相談する。
・自宅でできる簡単な運動を教えてもらう。
・歩行訓練や介助方法についてアドバイスをもらう
・立ち上がりや移動のサポート方法を学び、家族も安全に介助できるようにする。
・認知症リハビリの活用
・認知症予防のためのプログラムを活用し、家族も関与できるよう相談する。
施設ごとの職員の配置基準と対応範囲

介護施設ごとの職員配置基準(法定基準)
介護施設では、施設の種類によって職員の配置基準が異なります。配置基準を理解することで、どの施設が適切か判断しやすくなります。
| 施設の種類 | 介護士の配置基準 | 看護師の配置基準 | 生活相談員 | 機能訓練指導員 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 利用者3人に対し1人 | 必須(24時間配置不要) | 必須 | 必須 |
| 介護付き有料老人ホーム | 利用者3人に対し1人 | 必須(施設による) | 必須 | 施設により異なる |
| グループホーム | 利用者3人に対し1人 | 原則なし | 必須 | 施設により異なる |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 配置義務なし | 原則なし | 必須 | 施設により異なる |
施設ごとの対応範囲の違い
・特別養護老人ホーム(特養)
・24時間体制で介護が受けられるが、医療ケアは限られる。
・要介護3以上の利用者が対象。
・介護付き有料老人ホーム
・介護スタッフが常駐し、手厚いケアが受けられるが費用が高め。
・看護師が常駐している施設も多い。
・グループホーム
・認知症の方が対象で、家庭的な環境で生活できる。
・少人数制で職員との距離が近い。
・サービス付き高齢者向け住宅
・介護サービスは外部委託のため、自立度の高い人向け。
・緊急時対応や生活相談などのサポートが受けられる。
介護施設での職員との関係を円滑にするコツ

家族として積極的に関わる
介護施設での生活をより快適にするためには、家族も職員と協力しながらサポートすることが大切です。
・定期的に面会を行う
・利用者の様子を直接確認し、職員とのコミュニケーションを深める。
・職員に感謝の気持ちを伝えることで、良好な関係を築く。
・職員に過度な要求をしない
・施設のルールを理解し、過剰な介護サービスを求めない。
・介護スタッフの業務範囲を把握し、無理のない範囲で協力を求める。
・施設の方針を理解する
・施設ごとのケア方針や規則を確認し、家族の希望とすり合わせる。
・必要に応じて、施設の相談員と話し合いながら調整する。
トラブルを避けるためのポイント
介護施設では、家族と職員の間で意見の相違が生じることもあります。スムーズに対応するためのポイントを紹介します。
・トラブルが発生した場合は冷静に対応する
・すぐに感情的にならず、事実確認を行う。
・職員と話し合い、解決策を模索する。
・他の家族とも情報共有を行う
・兄弟姉妹や親族と定期的に情報を共有し、施設との関係を円滑にする。
・家族が協力することで、職員への負担を軽減できる。
・施設の変更を検討する場合
・施設のサービスや対応に不満がある場合は、相談員や施設長と話し合う。
・どうしても改善されない場合は、別の施設を検討することも選択肢となる。
公式LINEでの無料相談サービスの案内
ハートでは老人ホーム紹介会社として高齢者住まいアドバイザー、ファイナンシャルプランナー、不動産終活士が在籍しており完全無料で適切な介護施設をお探ししご提案しております。詳しく知りたい方、どの施設が最適かわからない方、自分に合ったサービスを探している方は、ハートの公式LINEからご相談ください。資格を持つ専門のスタッフが、あなたのニーズに合った情報を提供します。
✨こちらから公式LINEに登録して、ご相談ください!よくある質問(Q&A)
まとめ
・介護施設には多くの職種があり、それぞれが専門的な役割を果たしている。
・家族が職員と適切なコミュニケーションを取ることで、より良い介護が受けられる。
・施設ごとの職員配置基準を理解し、適切な施設を選ぶことが大切。
・トラブルを避けるために、家族と職員の協力体制を整えることが重要。
・定期的な面会や相談を通じて、利用者の快適な生活を支えていく。
介護施設は、利用者の生活の場となる大切な空間です。職員と家族が協力しながら支えていくことで、より充実した生活を送ることができます。家族としても施設の職員との関係を大切にし、利用者が安心して過ごせるように努めましょう。
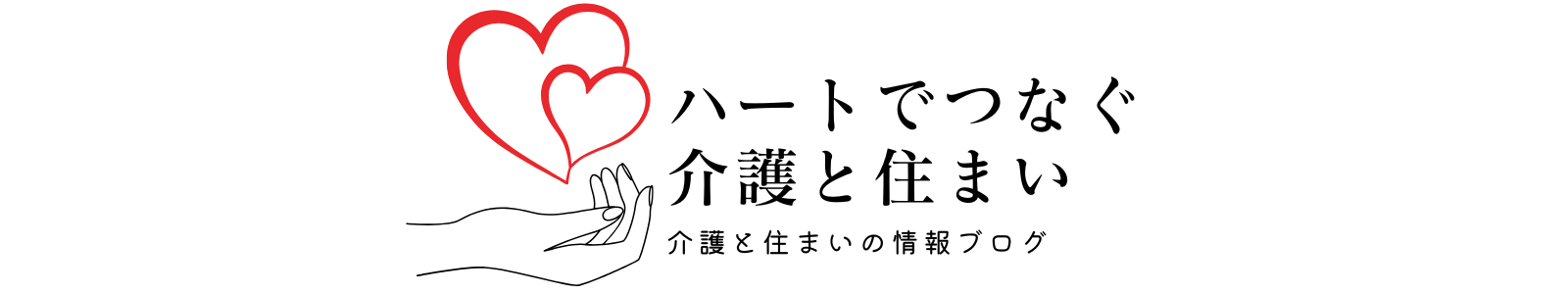




コメント