【在宅介護の必須スキル】自宅での褥瘡(床ずれ)予防と介護食の工夫

在宅介護において、被介護者の健康と生活の質を維持するためには、日々の細やかなケアが不可欠です。特に**「褥瘡(床ずれ)」と「誤嚥」**は、命に関わることもあり、正しい知識と技術が求められる二大リスクです。家族の努力や愛情だけでは、これらのリスクは防げません。
本記事では、在宅介護で最も重要な身体的なケア技術に焦点を当て、床ずれの原因と予防のための体位変換・ポジショニングの方法、そして誤嚥を防ぐための**「介護食(嚥下食)」の簡単な調理と工夫**について、すぐに実践できる知識を提供します。
まずは、この二大リスクのメカニズムと深刻度を理解しましょう。対策は、リスクの正しい理解から始まります。
褥瘡(床ずれ)のリスク
褥瘡は、体重がかかる体の部位の血行不良によって、皮膚の細胞が壊死してしまう状態です。主に仙骨部(尾てい骨)、かかと、肩甲骨など、骨が突出している部分に発生します。
・危険性: 初期は皮膚の赤みですが、進行すると皮膚が深くえぐれ、細菌感染を引き起こします。重症化すると敗血症などの命に関わる状態に繋がり、長期入院が必要になることもあります。
誤嚥のリスク
誤嚥とは、食べ物や飲み物、唾液が誤って食道ではなく気管に入ってしまうことです。
・危険性: 誤嚥によって口腔内の細菌が肺に運ばれると、誤嚥性肺炎を引き起こします。これは高齢者の肺炎の多くを占めており、日本の高齢者の主要な死亡原因の一つです。熱が出ないなど症状が出にくいケースもあり、気づいたときには重症化している危険性があります。
褥瘡予防は、体にかかる圧力を分散し、皮膚を清潔に保つという基本の徹底にかかっています。
体圧分散(Turning:体位変換)
清潔保持(Tidiness:皮膚ケア)
皮膚が汚れていたり、蒸れていたりすると、バリア機能が低下し褥瘡の原因となります。
・排泄後のケア: 失禁などがあった際は、すぐに清拭し、微温湯で優しく洗浄することが必須です。石鹸カスを残さないよう、しっかり洗い流しましょう。
・摩擦を避ける: 寝具のシワや、体位変換の際に皮膚を強く引きずる行為は、皮膚を傷つけ褥瘡の原因となります。体位変換は、手のひらで体を持ち上げるように行い、摩擦を避けます。
・保湿ケア: 清潔にした後は、皮膚の乾燥を防ぐための保湿剤を優しく塗布し、皮膚のバリア機能を維持します。

栄養管理(Total Nutrition:栄養)
実践編:誤嚥を防ぐ「介護食(嚥下食)」の簡単な工夫
安全に美味しく食べてもらうためには、食事前の準備から食後のケアまで、正しい知識が必要です。
食べる姿勢の工夫
食事の安全性を高める最も簡単な工夫は、姿勢を変えることです。
・理想的な姿勢: 椅子や車椅子、ベッドに座る際は、背筋を伸ばし、少し顎を引いた前傾姿勢(30度程度)が誤嚥を防ぐ理想的な姿勢です。リクライニングベッドの場合は、30度から60度に背上げし、足の裏がしっかりと床やフットボードに着くように調整します。
・食事前の口腔体操: 唾液の分泌を促し、嚥下に関わる筋肉を動かすために、食事前に**「パタカラ体操」**などの口腔体操を行うと効果的です。
家庭でできる介護食の簡単な調理テクニック(介護食 レシピ 嚥下)
誤嚥しやすい食材を避け、食べやすい形状に加工する工夫です。
・「とろみ付け」の活用: サラサラした液体(水、お茶、汁物)は最も誤嚥しやすいため、市販の**「とろみ剤」**を必ず使用しましょう。水やお茶に粘度をつけることで、ゆっくりと食道を流れるようになります。
・まとまりやすさの工夫: パサつく食材(鶏むね肉、パサパサしたパン、ひき肉)や、口の中でバラバラになる食材は、餡(あん)やマヨネーズ、ポタージュソースなどを加えてしっとりさせ、まとまりやすい形状にします。
・避けるべき食品: 喉に張り付きやすいもの(餅、のり)、口の中でバラバラになるもの(炒り卵、煎餅)、繊維質の多いもの(生の葉物野菜)は極力避けましょう。
公式LINEでの無料相談サービスの案内
ハートでは老人ホーム紹介会社として高齢者住まいアドバイザー、ファイナンシャルプランナー、不動産終活士が在籍しており完全無料で適切な介護施設をお探ししご提案しております。詳しく知りたい方、どの施設が最適かわからない方、自分に合ったサービスを探している方は、ハートの公式LINEからご相談ください。資格を持つ専門のスタッフが、あなたのニーズに合った情報を提供します。
食後のケア
誤嚥性肺炎の主な原因は、口腔内の細菌です。
・徹底した口腔ケア: 食後すぐに歯磨きや義歯の清掃を行い、食べかすや細菌を口の中に残さないようにします。舌苔の除去も忘れずに行いましょう。
・食後の姿勢: 食後2時間程度は、横にならず、座った姿勢を保つことで、胃の内容物の逆流による誤嚥を防ぐことができます。
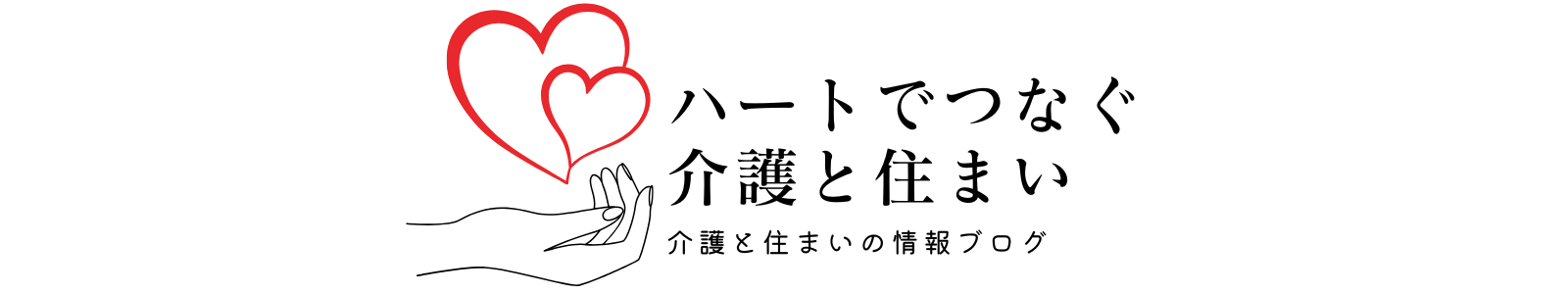




コメント