はじめに

親の介護が始まったとき、最も心を痛めるのが兄弟姉妹間のトラブルではないでしょうか。
特に費用負担の問題はデリケートで、「介護の手間」と「金銭的負担」のバランスを巡って、これまで仲の良かった兄弟でも感情的な対立に発展しがちです。
「誰が費用を出すべきなのか?」「なぜ自分ばかりが負担しなければならないのか?」という疑問を抱えているあなたへ。この記事では、金銭トラブルを未然に防ぐための**「公平な分担」**に向けた話し合いの具体的な進め方と、法的な考え方を専門家の視点から解説します。
知っておきたい基本の考え方:民法上の「扶養義務」とは
兄弟姉妹間で費用分担を話し合う前に、法的な前提知識を共有しましょう。この原則を理解しておくことで、感情論ではなく客観的な議論の土台を作ることができます。
民法上、子どもには親を扶養する**「扶養義務」があります。ただし、これは「自分の生活レベルを落としてでも」親を支える義務(生活保持義務)ではなく、「自分の生活に無理のない範囲で」**支える義務(生活扶助義務)と解釈されています。
つまり、親自身の年金や貯蓄が不足し、経済的に困窮した場合、子どもたちはそれぞれの生活を破綻させない範囲で親の生活を支える義務を負う、ということです。
負担割合の原則は「経済状況」
この義務に基づき、費用負担の割合は、**各扶養義務者(兄弟姉妹)の経済状況(収入や資産)**に応じて決めるのが原則とされています。
「子どもの数が3人だから3等分(頭割り)」が必ずしも公平ではないのは、このためです。経済的に余裕のある者が多めに負担し、そうでない者は負担を少なくするという考え方が、法的な公平性の基本です。
紛争を未然に防ぐ!公平な費用分担のための6つのステップ

感情論ではなく、事実と原則に基づき話し合いを進めるための具体的な6ステップです。冷静に、そして客観的に情報を整理することから始めましょう。
Step 1:親の資産状況の「完全開示」
まず、親自身の資産がどこまであるかを正確に把握し、兄弟間ですべて開示・共有します。。
・確認すべき情報: 預貯金(すべての銀行口座)、年金収入額、所有不動産、生命保険の契約状況、有価証券など。
・目的: これが「親がどこまで自己負担できるか」の基準になります。親の資産だけで賄えるなら、子どもの負担は発生しません。不透明な部分があると、必ず「あの兄弟が親のお金を勝手に使っているのでは?」という疑念に繋がり、トラブルの元となります。
Step 2:介護費用の「正確な見える化」
在宅介護サービスや老人ホームの費用について、月々の費用総額を正確に計算し、共有します。
・計算すべき項目: 施設であれば、居住費、食費、管理費、介護保険の自己負担分。在宅であれば、サービス費用、医療費、オムツ代などの雑費。
・ポイント: 見積書や請求書など、客観的な数字を元に話し合うことが重要です。曖昧な「だいたいこれくらい」は避けましょう。
Step 3:不足する金額の特定
Step 2の月々の費用総額から、Step 1の親の年金収入を差し引き、**「毎月不足する金額」**を明確にします。
・この不足額こそが、子どもたちが分担しなければならない金額です。この数字を叩き台として、具体的な分担交渉に入ります。
Step 4:各自の「人的貢献度」の確認と評価
金銭的な負担だけでなく、**時間や労力といった金銭以外の貢献(人的負担)**を可視化します。
・例: 施設への送迎担当、週に数回の見守り訪問、通院の付き添い、役所や施設との手続き代行など。
・目的: 介護負担が一人に集中している場合、その「手間」を後の金銭分担の調整要素として評価します。このステップは、**「私は介護の手間をかけているのに、お金まで出すのは不公平だ」**という感情的な不満を解消するために不可欠です。
Step 5:収入に応じた負担割合の決定
step 3で特定した不足額について、兄弟姉妹それぞれの収入や資産を考慮し、負担割合を決定します。
・理想的な考え方: 経済的に余裕のある兄弟が多めに負担し、子育て中や住宅ローンなどで生活が厳しい兄弟の負担を軽減します。
・調整の実施: Step 4で評価した「人的貢献度」が高い兄弟は、金銭的な負担割合を低くする、といった調整を行います。
Step 6:「取り決め書」の作成と署名
決定した事項を、**必ず文書(合意書・取り決め書)**に残し、全員が署名します。
・記載事項: 決定した分担額、毎月の支払い方法、支払い期日、および「親の資産状況に変化があった際の見直し時期」**。
・重要性: 口約束では、時間が経つにつれて「言った言わない」のトラブルになります。文書化は、全員が合意した事実を明確にし、後のトラブルを防止する最も有効な手段です。
3. 調整のポイント:「お金」と「手間」のバランスの取り方
多くの兄弟間トラブルは、「お金」を出す人と「手間(労力)」を出す人が分かれている場合に発生します。このバランスをどう取るかが、話し合いの鍵です。
人的負担の評価
介護の手間を負っている人に対して、金銭的な負担を減らすという形で**「手間を金銭で評価・補填する」**視点を持つことが大切です。例えば、介護を主導する人には金銭負担を免除し、遠方に住む兄弟がその分を多めに負担するという形が考えられます。
第三者の冷静な視点の活用
金銭や介護の話題は、家族間では感情的になりがちです。話し合いがスムーズに進まないと感じた場合は、第三者の専門家(ケアマネジャー、または弊社の相談員など)に家族会議への同席を依頼することも検討してください。客観的な情報提供や施設費用の試算を通じて、冷静で公平な合意形成をサポートできます。
公式LINEでの無料相談サービスの案内
ハートでは老人ホーム紹介会社として高齢者住まいアドバイザー、ファイナンシャルプランナー、不動産終活士が在籍しており完全無料で適切な介護施設をお探ししご提案しております。詳しく知りたい方、どの施設が最適かわからない方、自分に合ったサービスを探している方は、ハートの公式LINEからご相談ください。資格を持つ専門のスタッフが、あなたのニーズに合った情報を提供します。
トラブルが解決しない場合の最終手段

もし、上記6ステップを踏んでも話し合いがどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所に**「扶養請求調停」**を申し立てるという最終手段もあります。調停では、裁判所の調停委員が間に入り、双方の経済状況を考慮して公平な負担割合を定めることになります。
しかし、時間や精神的な負担を考えると、できれば家族の話し合いで解決するのが最良です。
親の介護や施設入居は、家族にとって大きな課題です。金銭が絡むデリケートな問題だからこそ、客観的な情報と冷静な視点を持って向き合うことが重要です。私たち専門の相談員は、お客様一人ひとりの状況に寄り添い、最適な施設選びだけでなく、費用や家族間の問題解決に向けたサポートも提供しています。
親御様の将来の暮らしについて、まずはお気軽にご相談ください。
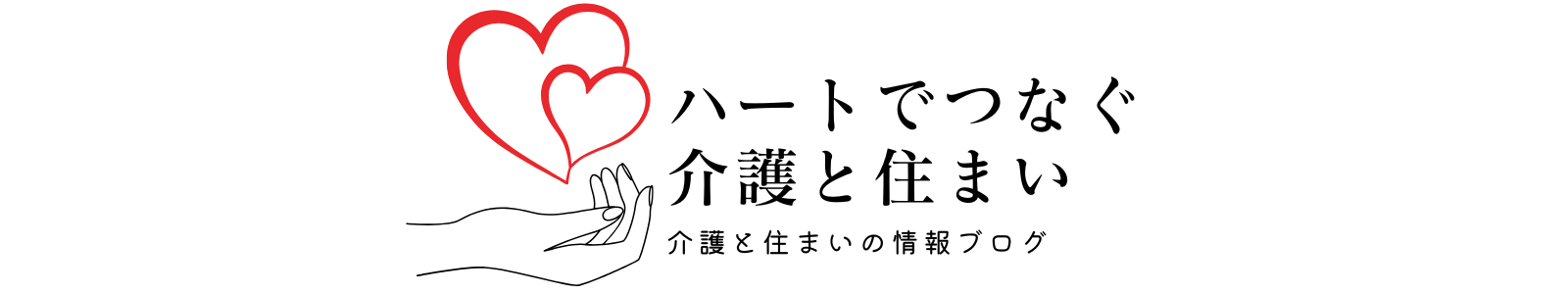




コメント