はじめに

親御様の介護費用や生活費を工面しようとしたとき、突然銀行や証券会社から「親御様の意思確認ができないため、口座を凍結します」と告げられることがあります。これは、認知症によって本人の意思能力が失われると、財産が犯罪などに利用されるのを防ぐために行われる、やむを得ない措置です。
この**「認知症 財産凍結」**のリスクは、親の入院費や介護施設の費用支払いをストップさせ、家族を窮地に追い込みます。
本記事では、このリスクを回避し、親の資産を安全に守り、必要なときに活用するための法的な3つの対策(成年後見制度、任意後見制度、家族信託)を比較し、それぞれの費用と手続きを分かりやすく解説します。
なぜ起こる?認知症による「財産凍結」のリスク
対策を講じる前に、なぜ銀行口座が凍結され、何ができなくなるのかを明確に理解しましょう
(1)銀行・証券会社の対応の原則
金融機関は、預金者本人の意思が確認できない状態(認知症など)で預金の引き出しや解約が行われると、不正な引き出しや悪用のリスクがあると判断します。これは、金融機関が預金者を守るための義務であり、たとえ家族であっても、名義人本人以外の取引は原則として停止されます。
・凍結によってできなくなることの具体例
(2)凍結を解除する唯一の方法
一度口座が凍結されると、金融機関が凍結を解除し、代理人による取引を認める唯一の方法は、家庭裁判所が選任した**「成年後見人」**が存在することです。つまり、認知症発症後に財産管理が必要になれば、必ず裁判所の手続きを経る必要があるのです。

対策【1】成年後見制度:発症後でも利用できる公的制度
すでに認知症が進行し、判断能力が不十分になってしまった後に利用できる、最も一般的な制度です。家庭裁判所に申し立てを行い、**本人の財産管理や身上監護(生活・介護・医療に関する契約)**を行う後見人を選任してもらいます。
メリットとデメリット(成年後見制度 費用)
| 項目 | 詳細 |
| メリット | 発症後でも利用可能であり、すでに認知症が進行している場合に必須となる。家庭裁判所が後見人を監督するため、財産が守られる安心感がある。後見人には、本人に代わって医療・介護の契約を行う身上監護権限がある。 |
| デメリット | 手続きが複雑で時間がかかる。後見人は原則、辞められない。後見人が選任されると、本人の財産は後見人の判断で管理され、家族が自由に使うことはできなくなる。後見人(親族以外)への報酬が発生し続ける。 |
費用の実態とランニングコスト
成年後見制度の大きな特徴は、継続的なランニングコストが発生することです。
対策【2】任意後見制度:発症前に「誰に頼むか」を決めておく
親御様が判断能力があるうちに、将来、認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、**信頼できる人物(任意後見人)**をあらかじめ選んでおく制度です。
メリットとデメリット
費用の実態とランニングコスト

対策【3】家族信託:家族に資産管理の権限を「託す」(家族信託 介護)
財産の「所有権」は親に残したまま、「管理・運用する権限」を家族に託す(信託する)手法です。裁判所を介さずに、家族内で柔軟に資産を管理したい場合に有効な手法として注目されています。
メリットとデメリット
費用の実態と初期費用
・初期費用:契約内容の設計、契約書の作成、公正証書作成、不動産がある場合の登記費用など、専門家への報酬(司法書士や弁護士)が中心となります。初期費用として数十万円~100万円以上かかる場合がありますが、月々のランニングコストはかかりません。
公式LINEでの無料相談サービスの案内
ハートでは老人ホーム紹介会社として高齢者住まいアドバイザー、ファイナンシャルプランナー、不動産終活士が在籍しており完全無料で適切な介護施設をお探ししご提案しております。詳しく知りたい方、どの施設が最適かわからない方、自分に合ったサービスを探している方は、ハートの公式LINEからご相談ください。資格を持つ専門のスタッフが、あなたのニーズに合った情報を提供します。
✨こちらから公式LINEに登録して、ご相談ください!よくある質問(Q&A)
結論:我が家に最適な対策はどれか?比較と推奨タイミング
3つの制度の特徴をまとめると、以下のようになります。
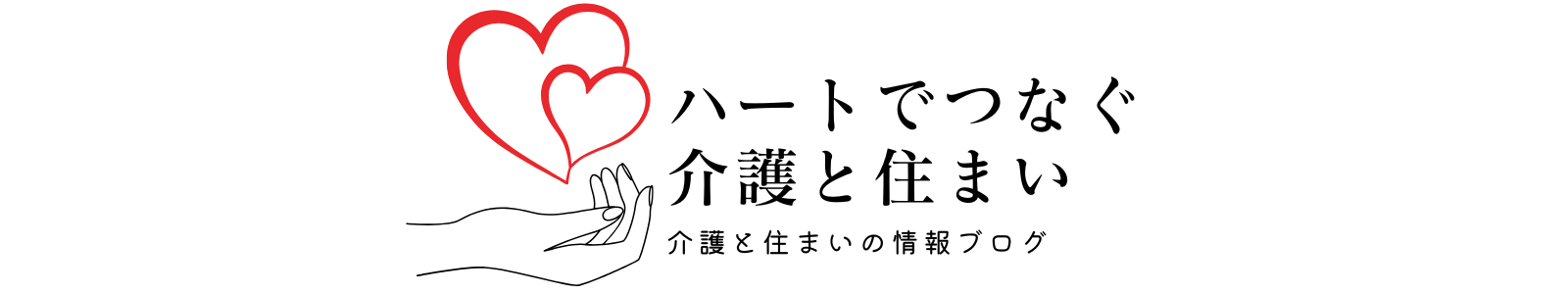




コメント